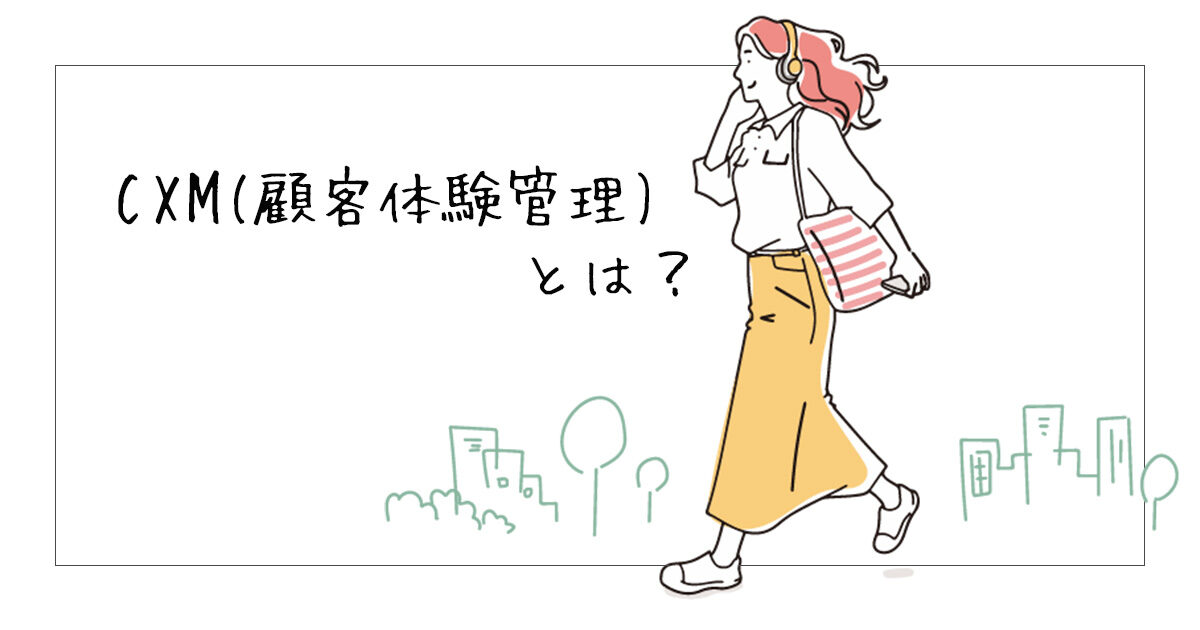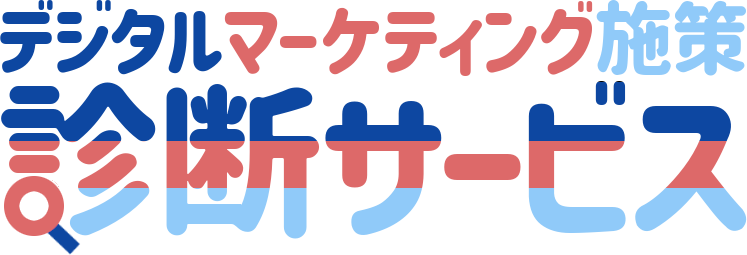「顧客体験(CX)」という言葉を耳にする機会が増えたのではないでしょうか。
商品やサービスの機能や価格だけでは差別化が難しい現代において、顧客一人ひとりの心に響く体験を提供することが、企業にとって重要な課題となっています。
CXを管理・改善し、最適化するための戦略が「CXM(Customer Experience Management)」です。
本記事では、なぜ今CXMが注目されるのか、AIがCXMにもたらすメリットなどをご紹介します。
CXM(顧客体験管理)とは?
CXMとは、「Customer Experience Management(顧客体験管理)」の略で、顧客体験(CX)を管理・改善し、顧客満足度やロイヤルティを高めるための戦略のことです。
商品やサービスの「スペック」や「価格」などの機能的価値だけではなく、その商品やサービスを購入することで得られる「満足感」「心地よさ」「感動」といった感覚的な価値を重視し、顧客との中長期的な関係構築を目指します。
CRMとの違い
CRMは「Customer Relationship Management(顧客関係管理)」の略で、顧客情報を一元管理し、顧客と良好な関係性を構築すること、またそのために使用する手法やツールのことです。
CXMとCRMは基本的な機能にいくつか似ている点もありますが、目的が異なります。
CRMは顧客との接点における数値を細かくデータベース化することで、LTVの最大化を目指し顧客のニーズに適したアプローチをすることが目的です。
一方CXMは顧客の感情を重視し、購買行動の全てのプロセスにおいて価値のある体験を作ることで、顧客ロイヤリティを高めていくことを目的としています。
CXMはCRMの次の段階の取り組みであるともいわれています。
CRMが注目された背景は1990年代に商品やサービスの競争激化により新規顧客の獲得が難しくなり、既存顧客を「個」としてとらえ、対応を見直す必要に迫られたことです。
しかし、2015年以降ネットが普及したことで顧客接点が多様化し、「〇〇カードをお持ちですか?」「△△もご一緒に購入いただければ割引できます」といったクロスセルを目的としたコミュニケーションは、時に顧客の感情にプラスとならず、関係性が悪化してしまうケースも少なくありませんでした。
そこで顧客の感情や生の声を大切にしようと生まれたのがCXMの考え方なのです。
CXMがなぜ重要なのか
多様な選択肢や価値観・ニーズがある現代では、機能的価値による差別化が難しいことから、感覚的な価値が購入の決め手となることが増えています。
購入時だけではなく、利用後まで考慮した一連の「体験」の価値を提供することで、顧客エンゲージメントを向上させる仕組み作りが重要です。
顧客体験の改善を地道に続けることで、商品やサービスのリピーターやファンを増やし、中長期的なLTV向上に繋げていくことができるのです。
また、同様に顧客との接点も多様化しています。
インターネットやSNSの進化により、顧客自身がポジティブ・ネガティブどちらの意見も自由に情報発信をし、拡散されることが当たり前になりました。
そのため、顧客の要望やクレームを把握し、分析することも大切な要素です。
AIの活用によるCXMの進化
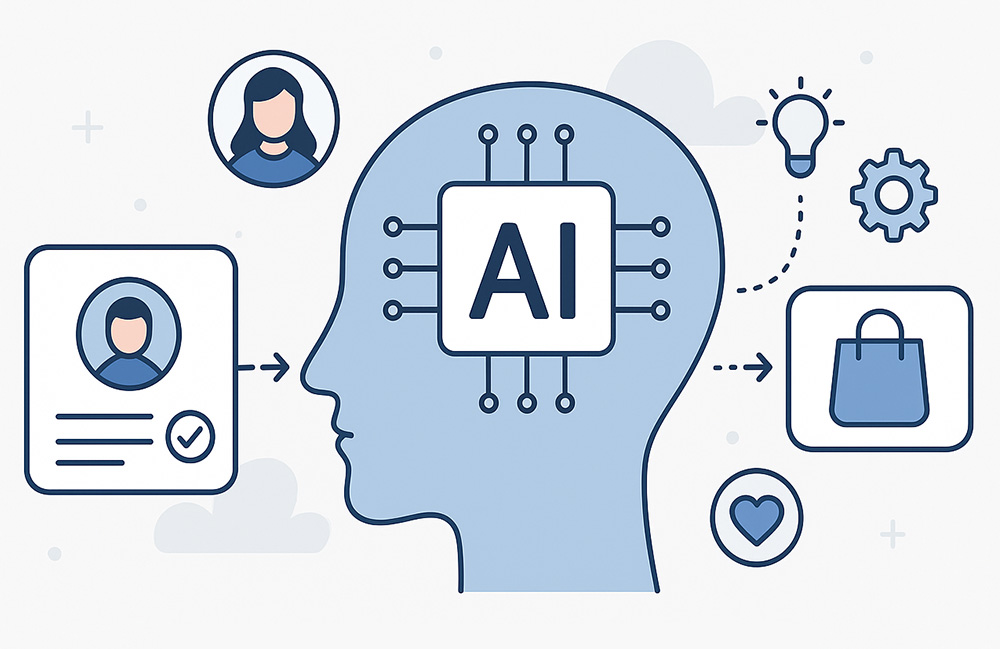
CXMは顧客一人ひとりに異なるシナリオを提供し、その人が求めている体験をレコメンドしていく世界です。
これまでは「年代」「性別」「地域」など大まかなセグメントで分けられていましたが、生成AIを活用することでデータに基づいたきめ細やかな対応が可能になります。
パーソナライズの高度化
AIを使えば膨大な顧客データ(行動履歴・購買履歴・SNSの発言など)を分析できるので、個々に合わせた最適な情報やレコメンドをリアルタイムで提供できます。
同じ商品やサービスでも顧客一人ひとりの状況や感情に合わせて提案が変わります。
例えば「平日の夜のスマホ利用時」「休日に家族と買い物をしている時」では異なる体験を提示したり、音声分析や感情分析によって「怒っている時」「楽しんでいる時」といった感情に合わせたレコメンドも可能です。
顧客対応の自動化・効率化
24時間365日対応のチャットボットやAIアシスタントを使うことで定型的なタスクを自動化することが可能です。
また、AIを活用すると瞬時に問い合わせ内容を要約したり、オペレーターへナレッジ提示することで業務効率化も実現できます。
顧客とのやり取りの中から、さらに高度なインサイトを見つけることもできます。
例えば、クレームの電話で怒っていたはずの顧客がオペレーターの対応により納得、さらには感動へと至り他の商品を追加購入するケースもあったりします。
人のオペレーターだけでは判断が難しい顧客感情をAIの音声分析やテキストマイニングを活用することで、顧客体験を高めた対応をすることができるようになるのです。
CXMを活用した事例
スターバックスコーヒージャパン
スターバックスコーヒージャパンが2019年から導入したのが「Mobile Order & Pay」です。
店舗で購入する際の「列に並んで待つ時間」を解消するためにスタートした施策で、アプリで事前に商品やカスタマイズ内容を選んで支払いを済ませ、受け取り時間に店舗へ行けば商品が受け取れるサービスです。
待ち時間だけではなく、後ろに並んでいる人が気になって注文しづらいという課題も解消できるため、一度利用した人は利用頻度が増える傾向にあるそうです。
また、オーダー時に最大10文字の「ニックネーム」を指定できる取り組みもしています。
顧客を番号ではなくニックネームで呼ぶことで、利便性だけではなく、スタッフとのコミュニケーションのきっかけとなり、特別感を感じてもらえます。
このような取り組みによって同社は「特別な体験」を提供し、顧客との関係性をより深めているのです。
オルビス
昨今注目されているのが、物を売るのではなく「体験」に特化した店舗です。
化粧品ブランドのオルビスが2020年から展開している「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」は商品を売らない体験型店舗がコンセプトです。
試すことに特化していて、顧客は専門機器を使った肌診断を受けることができたり、メイクアップアイテムを自由に試せるパウダールームもあります。
オルビスユーのローションボトルをオリジナルデザインにカスタマイズしたり、アプリと連動し「パーソナルカラー」に合わせたメイクレッスンを受けられたり、顧客個人に合わせた「特別な体験」ができるようになっています。
Netflix
Netflixはこれまでにないパーソナライズされたレコメンドシステムを提供し、CXMに成功した代表例といえるでしょう。
単に過去に視聴した作品の続編や監督・役者が同じである作品だけではなく、ユーザーが好む作品やジャンルを細かく把握することで、的確な提案をします。
この機能によってユーザーは自ら好きなコンテンツを探さなくても、好みに合ったコンテンツを見つけることができるのです。
このことで、継続的なサービス利用、ひいては高い顧客満足度に繋がっています。
まとめ
これからのコマースやマーケティングを考える上で大切なのは、商品やサービスを通して「体験の価値を提供できるか」です。
CXMを導入し、データとAIを活用することで顧客一人ひとりに合わせたパーソナライズな対応が今後ますます求められていくでしょう。
AIが出した解析結果を人間がどのように活かし、顧客体験を設計するかも重要なポイントです。
CXMが実現できれば、顧客と長期的な信頼関係を築き、ロイヤリティを向上させることができます。
ソーウェルバーでは、AIを使ってSNS投稿データを分析し、顧客のリアルな声やトレンドを把握できる新しいツール「HAKURAKU」を提供しています。
顧客の感情や行動の背景にまで踏み込んだCXMの実現への一助になればと思いますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。