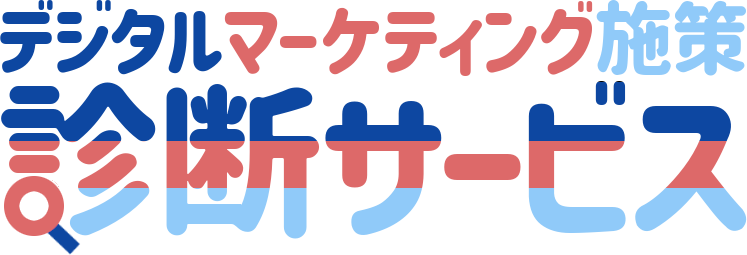マーケティングの世界には、多くの経験則や理論がありますが、その中でも「ダブルジョパディの法則」は特にマーケットシェアと顧客の購買行動の関係性を示す重要な法則です。文字通り「二重の不利(Double Jeopardy)」と言われるこの現象は、商品の規模が小さいほど、顧客数と購入頻度の両方で不利な状態にあることを示しています。本記事では、この法則の概要、背景、そしてマーケティング戦略への応用についてわかりやすく解説します。
- 目次
- ダブルジョパディの法則とは?
- なぜダブルジョパディの法則が起きるのか?
- 従来のマーケティング理論との違い
- ダブルジョパディの法則を考慮したマーケティング戦略のポイント
- 実践例でみるダブルジョパディの法則
- まとめ
ダブルジョパディの法則とは?
ダブルジョパディの法則は、ブランドの市場シェア(浸透率)と顧客のロイヤルティ(購入頻度)が強く連動しているという経験則です。簡単に言うと、ブランドの規模が小さいほど、顧客数が少ないだけでなく、1人あたりの購入頻度も低い傾向にある、ということです。
この関係性は、日本国内外の多種多様な市場で繰り返し観察されており、消費財からサービス、さらにはBtoBの世界に至るまで幅広く適用されています。つまり、大手ブランドは自然と多くの顧客を持ち、その顧客が平均的により多く購入しているため、売上を拡大しやすい構造にあるのです。
なぜダブルジョパディの法則が起きるのか?
顧客がブランドを選ぶ際、認知のされやすさや購入可能な機会が大きく影響します。市場での露出が少ないブランドは、そもそも検討すらされにくく、購入者数が限定されます。
また、購入頻度の面でも、認知度や販売チャネルの豊富さから生まれる「自然な購入回数」の差が表れます。多くの顧客に支持される大手ブランドは、より定期的に購入される機会が多いのに対し、小規模ブランドは顧客の利用頻度が相対的に低い状態が続くのです。
このため、小規模ブランドは「買ってもらう顧客数」と「買ってもらえる回数」の両方で二重に不利となる、つまりダブルジョパディの状態に置かれています。
従来のマーケティング理論との違い
これまでの多くのマーケティング戦略は、「忠実なロイヤルカスタマーを育成することが成長の鍵」として説明されてきました。しかしダブルジョパディの法則が指摘するのは、実際には市場でのロイヤルティの高さは「顧客数の多さ」によって自然に生まれる傾向が強いということです。
言い換えれば、ロイヤルティを意識的に高める努力の前に、まずは「多くの人に使ってもらう」ことが市場シェア拡大の本質的な鍵である点が重要となります。
ダブルジョパディの法則を考慮したマーケティング戦略のポイント
顧客数の増加に注力する
積極的な認知拡大や販路開拓で、まずはブランドの浸透を高めることが先決です。
販売機会と接点を多様化・強化する
オフライン、オンライン、イベント、SNSなど多様なチャネルで商品やサービスを触れてもらう場を増やします。
リピート促進は顧客基盤の拡大に続く戦略
購入頻度を上げる施策は大切ですが、多くの顧客に浸透しなければ効果は限定的です。
小規模ブランドのニッチ戦略は慎重に
浸透率の低さが前提のため、良質なロイヤル層の構築は困難。まずは浸透率向上策の検討を優先すべきです。
実践例でみるダブルジョパディの法則
大手飲料メーカーの戦略
豊富な販売チャネルとテレビ広告による認知拡大で、多くの顧客を獲得。それに伴い、購入頻度も自然と上昇し、強固なブランドポジションを築きました。
スニーカーブランドの浸透拡大
人気アスリートの起用やSNSでのバイラル拡散を活用し、短期間で新規購入層を増やした結果、リピート購入者も増加し売上が拡大。
中小企業の地元ブランド
地域限定の販促活動やイベント参加で認知を広げ、少しずつ購入者数を増やしながら、顧客との接点を強化している例もあります。
まとめ
ダブルジョパディの法則は、ブランドの市場シェアがいかに顧客の購入行動に影響を及ぼすかを示す重要な原理です。マーケターはこの法則を理解し、まずはブランドの浸透率向上を最優先に据えるべきです。顧客基盤が大きくなれば、ロイヤルティの向上も自然と期待できるため、施策の効果的な段階的展開が可能になります。
ブランド力強化には、数を増やし、買ってもらう機会を最大化することが不可欠。小規模ブランドや新規参入企業ほど、この法則を踏まえた戦略策定が成長の鍵となるでしょう。
ダブルジョパディの法則を理解し、顧客数や購入頻度の重要性を押さえたら、さらにリアルな顧客の声を活用して戦略を練ることが成功のカギとなります。
SNS投稿データをAIで分析し、具体的なニーズやトレンドを把握できる「HAKURAKU」は、そのための強力なツールです。
ぜひマーケティング施策の精度向上にお役立てください。