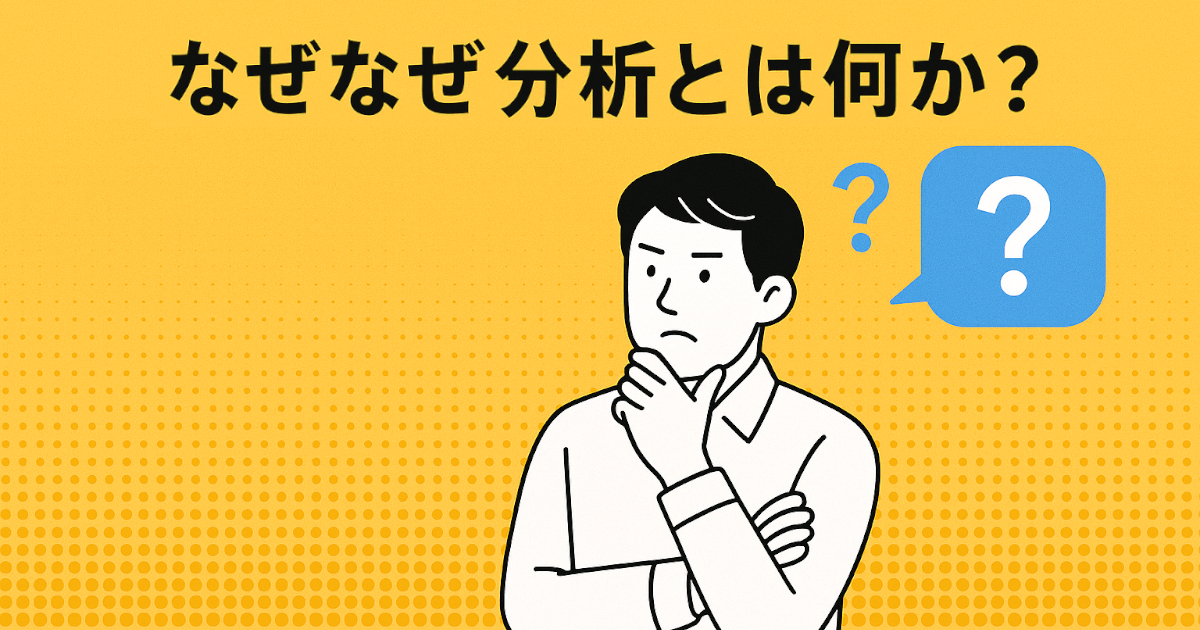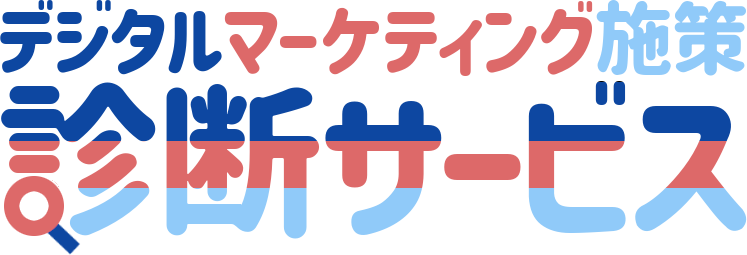AI技術やデジタル化が進む現代においても、現場の問題解決や業務改善の本質は「なぜ?」を問い続ける姿勢にあります。なぜなぜ分析は、トヨタ生産方式で生まれ、今や製造業のみならず多様な業界で活用される根本原因追求のための手法です。本記事では、なぜなぜ分析の基本から実践ポイント、注意点までを体系的に解説します。
なぜなぜ分析とは
なぜなぜ分析とは、発生した問題に対して「なぜ?」と繰り返し問いかけることで、表面的な原因ではなく根本的な原因(真因)を特定し、再発防止や本質的な改善につなげるための分析手法です。一般的には5回「なぜ?」を繰り返すことが推奨されており、英語では「Five Whys」とも呼ばれます。
この手法は、トヨタ生産方式(TPS)の中核をなす考え方の一つであり、単なる問題解決ツールにとどまらず、組織全体の改善文化を醸成する基盤ともなっています。
なぜなぜ分析の目的と効果
根本原因の特定
表面的な原因にとどまらず、問題の本質に迫ることで、的確な対策を導き出せます。
再発防止
真因に基づく対策を講じることで、同じ問題の繰り返しを防ぎます。
組織力の向上
問題の共有と改善策の検討を通じて、組織全体の学習意欲や問題解決能力が高まります。
ムダの削減・効率化
根本的な問題解決により、業務のムダやコストを削減できます。
なぜなぜ分析の進め方
問題の明確化
- 解決したい「問題」をできるだけ具体的に定義します。
- 例:「納期遅れが発生した」ではなく「Aプロジェクトで2週間の納期遅れが発生した」など。
問題の経緯・背景を把握
- 問題が起こった経緯や背景を整理し、全体像を把握します。
- 事実に基づいた情報収集が重要です。
「なぜ?」を繰り返し問いかける
- 問題に対して「なぜ?」を繰り返し、原因を深掘りします。
- 一般的には5回程度が目安ですが、真因にたどり着くまで繰り返します。
- 各回答が前の「なぜ?」と論理的につながっているかを確認します。
真因に対する対策を立案
- 特定した根本原因に対して、実現可能な解決策を考えます。
- 対策は現場で実行できる具体的なものにします。
対策の実行と効果検証
- 立案した対策を実行し、効果を検証します。
- 問題が解決しない場合は、再度「なぜ?」に立ち戻り、分析をやり直します。
なぜなぜ分析の実践例
製造現場での事例
事象:製品の一部にキズがついて出荷停止
- なぜ? → 製造ラインの一部に突起物があった
- なぜ? → メンテナンス時に取り外し忘れた部品が残っていた
- なぜ? → チェックリストに該当項目がなかった
- なぜ? → メンテナンス手順書が最新版に更新されていなかった
- なぜ? → 担当者変更により引き継ぎがされていなかった
このように、表面的な作業ミスだけでなく、運用フローやマニュアル体制といった「仕組みの課題」にまで踏み込むことができ、再発防止策(手順書更新・チェック体制の見直し)につながります。
成功のポイントと注意点
問題・原因は具体的に
抽象的な表現や状況説明ではなく、現場で改善可能な具体的な事象・原因を設定します。
個人の責任に帰着しない
「担当者がミスした」など個人の資質や責任にせず、仕組みや環境の問題に目を向けます。
客観的・多角的な視点で分析
主観や先入観にとらわれず、事実に基づき複数人で分析するのが効果的です。
「なぜ」の回数にこだわりすぎない
5回に限らず、真因にたどり着くまで繰り返すことが大切です。
解決策は実現可能なものに
現場で実行できる具体的な対策を立案します。
根本的に解決できない原因にしない
「景気が悪い」「忙しかった」など、自分たちでコントロールできない要因に帰着しないよう注意します。
まとめ
なぜなぜ分析は、問題の本質を見極め、再発防止や業務改善につなげるための強力な手法です。表面的な原因にとどまらず、真因を追求し、実現可能な対策を講じることで、組織全体の成長と顧客満足度の向上に寄与します。現場での実践を通じて、なぜなぜ分析の効果を最大限に引き出しましょう。
問題の本質を深掘りし、的確な仮説立案や顧客理解をさらに高めたい方には、SNSデータを活用した分析・考察ソリューション「HAKURAKU」もおすすめです。
HAKURAKUは、生成AIを活用してSNS投稿データからユーザーの声を素早く分析し、新たな仮説の立案や検証を効率的にサポートします。
膨大なデータから根拠ある示唆を短時間で抽出できるため、なぜなぜ分析で見つけた課題のさらなる深掘りや、マーケティング施策の精度向上にも役立ちます。
現場の課題解決や仮説検証に、ぜひHAKURAKUをご活用ください。